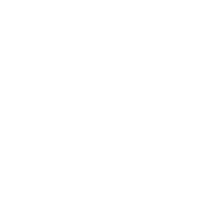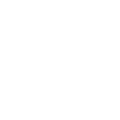各学科課題研究テーマ
看護学科:臨床の知
ナイチンゲールは、「看護はアートであり、科学である」と明言しています。看護は、科学の「客観性」「論理性」「普遍性」を重んじ、エビデンスに基づいた実践です。しかしながら、患者の心や家族に寄り添い、患者ひとりひとりと向き合うその時、その場面をとても大切にしています。今回の発表では、学生たちが看護実践を通し学んだ臨床の知を報告します。
理学療法士学科:臨床へのプロローグ
理学療法士学科ではこの研究大会のテーマを“臨床へのプロローグ”としました。学生たちは間もなく臨床で働くこととなりますがこの大会はプロローグ=序幕なのです。根拠のある医療を提供するためにも、医療人として社会人として心身を整え胸を張ってこの大会に臨みます。
作業療法士学科:作業療法の可能性
鳥取県は超高齢化社会に突入し、介護予防などの分野において医療人の参加が求められています。今回、レクリエーションを始め、気持ちをサポートすることや身体機能面への支援、学習効果などについてこれからの作業療法の可能性を拡げるべく学生が研究しました。それにより、鳥取県で作業療法に関わる全ての人々が豊かになる社会を思い描きました。
言語聴覚士学科:私たちで作る地域の未来
言語聴覚士の臨床は、言語、聴覚の障害、摂食・嚥下の障害など幅広く、乳幼児から高齢者の方までを対象としています。学生は、地域の方がそれぞれの地域でよりよい生活を送るための効果的な支援、また地域のニーズについて、調査や研究を進めてきました。“地域の方のため”に、「私たち」が作る地域の未来に向けて取り組んだ発表です。
口述演題
-
-
脳性麻痺の患児の看護 ~個人の特性に応じたアプローチの必要性~
-
地域で寄り添うコミュニケーション支援 ~失語症がある人の日常から考えよう~
-
オーラルディアドコキネシスの教示方法および測定方法について
-
色の変化が作業能率に与える影響
-
新規ユニバーサルスポーツの考案 ―スポーツで心と体を健康に作業療法の視点から―
-
運動前における寒冷刺激の有用性の検討 ~最大筋出力の関係性に着目して~
-
「バランス能力の圧迫刺激による効果・リズミックスタビ ライゼーション効果の相互比較について」
ポスター演題
-
終末期の患者の看護 ~疼痛のある患者に対する精神的安楽に向けた看護の効果~
-
残存機能を活かした食事援助 ~パーキンソン病患者との関わりを通して~
-
生活史に寄り添った苦痛緩和 ~心の休まる時間を提供するには~
-
誤嚥性肺炎を繰り返す患者の看護 ~食べることが好きな患者に対する関わり~
-
地域における言語聴覚士の役割の考察 ~学内施設「ことばの相談室」利用者アンケートより~
-
保育現場における構音不明瞭な幼児の対応について 現状と課題~保育士への調査から~
-
障がい者の雇用促進を中心に理想の街づくりを目指す
-
学校生活におけるストレスと性格との相関について
-
学習に集中する事が苦手な児童に関った症例
-
脊柱後彎変形と作業効率の関係性について
-
低負荷,低速度における上腕二頭筋の筋力増強
-
動的バランス・踏み出し能力に影響を与える姿勢制御戦略
-
浮き趾が若者に及ぼす影響
-
呼吸機能からみたポジショニングの検討