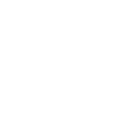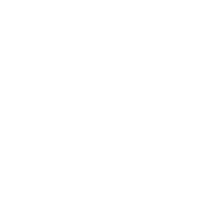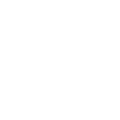残存機能を活かした食事援助 ~パーキンソン病患者との関わりを通して~
はじめに
パーキンソン病は、ふるえ(振戦)、動作緩慢、小刻み歩行など運動症状を主とする神経の変性疾患である。その症状は日常生活に影響を及ぼすため、意欲とQOL向上に向けた日常生活動作の獲得と維持は重要である。今回、大腿骨頸部骨折で入院中のパーキンソン病患者に対し、残存機能を活かした食事動作の方法を実践し、生活への意欲を引き出すことができたので報告する。
対象と方法
患者:A氏、80歳代、男性
診断名:大腿骨頸部骨折
家族構成:子ども4人は別世帯で生活しており、妻と2人で20年間施設入所
既往歴:脳梗塞後遺症による左半身麻痺、パーキンソン病
入院後の経過:外出時の転倒により大腿骨頸部骨折と診断。人工骨頭置換術施行後、早期離床とリハビリテーションを実施。
看護の実際・結果
入院5日目に手術が行われ、術後1日目より車椅子に移乗し、デイルームで食事を摂取された。移乗時に苦痛表情がみられたが疼痛に対する訴えはなく、自力で全量摂取できたが、「このまま食事も自分でできなくなるのかな・・・」という発言があった。A氏にとって食事動作が安楽かつ自立しておこなえることが、生活への意欲につながるのではないかと考えた。そこで、車椅子へ移乗した際は姿勢や足底の位置を整え、安楽かどうか患者に確認した。特にパーキンソン病の症状である、筋固縮により、上肢の動きが緩慢であることから、食事に1時間を要し、疲労感の訴えがあった。またA氏は麻痺のない右手だけで摂取しており、スプーンで食事をすくう際に食器が動くことも時間を要す原因だと考え、皿の下に滑り止めマットを敷き、スプーンの持ち手にはマット素材を太めに巻いた。するとスプーンを握りやすくなり、すくい上げる動作もスムーズに行え、疲労感の訴えが減少した。また、「これはいいな」と明るい表情がみられた。援助の実施前には言語聴覚士と一緒に、摂食動作を観察し、自助具の使用具合を確認し検討した。
考察
「食べる」ということは、人間の基本的欲求であり、高齢者の意欲や活動にも影響を及ぼす、なくてはならない行為である。A氏が麻痺のない右手だけで食事が摂取しやすいよう工夫することで疲労感が軽減したことが推察される。そして、自己効力感の向上につながり、生活への意欲も向上したのではないかと考える。今、自立している食事摂取が、今後も楽しく安全に実施できるよう、老いと意欲のギャップや、日々揺れる気持ちを受け止めながらケアしていくことが大切である。ミルトン・メイヤノフは「ケアの本質」の中で「一人の人格をケアするとは、最も深い意味でその人が成長すること、自己実現することを助けることである」1)と述べている。患者の思いを傾聴し、日々の生活の中での充実感や、楽しみを見出すことがA氏のQOL(生活の質)の向上につながったと考える。
まとめ
A氏の事例を通して患者の残存機能に働きかける援助を行うことで、尊厳が守られ、その人らしい生活を送るための意欲を引き出すことができた。
参考文献・引用
- 1)ミルトン・メイヤノフ:田村真、向野宜之 訳「ケアの本質」
- 2)成人看護学:脳・神経