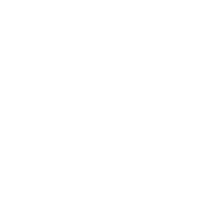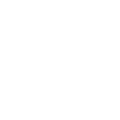要支援・要介護高齢者の外出頻度に関わる環境因子の検討
はじめに
現在日本は超高齢社会になり,要介護者・要支援者が増加傾向にある.健康状態の悪化を未然に防ぐには,要介護者等の健康状態を把握する必要がある.藤堂ら1)は「外出頻度は地域高齢者の健康指標の1つであり,高齢者の健康状態を維持するためには外出頻度を増加するべき」と述べている.また,加藤らは2)「外出頻度を増加させるためには,身体機能のみではなく,環境因子に着目する必要がある」と述べている.これらのことから,環境因子を1道路周辺環境(物的障害),2目的地数,3目的地までの距離と設定し,外出頻度と環境因子の関係性について調査及び分析を行い,外出頻度を増加させる環境因子を明らかにすることを目的とした.
対象と方法
1)対象:鳥取市内のデイサービスに通われている60歳から90歳以上の高齢者27名.対象者は要支援1.2,要介護1.2で,改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)が20点以上,普段の移動は独歩,福祉用具などを使用し,FIMにおける「移動」が4以上とする.
2)方法:アンケート調査にて個別のヒアリング調査を実施した.アンケート内容は1性別,2年齢,3FIM(移動能力),4家族構成,5住宅形態,6移動動作レベル,7外出状況,8外出内容,9目的地数,10道路周辺環境の10項目とした.
3)解析方法:アンケート結果は外出頻度を順序尺度,環境因子を名義尺度とし,検定にはカイ2乗検定を用いた.
結果
アンケートは20名(男性:11名,女性:9名)から回答が得られた(回収率74%).外出頻度は週5日以上5名,週3~4日程度3名,週1~2日程度6名,外出なし6名であった.階段・段差が4名,坂道2名,その他5名(横断歩道など),特になし9名であった目的.地数は,5箇所以上2名,3~4箇所7名,1~2箇所10名,0箇所1名であった.目的地までの距離は,500m以内4名,1km未満4名,1km以上12名であった.カイ2乗検定を用いて検定した結果,1道路周辺環境(p=0.57>0.05),2目的地数(p=0.65>0.05),3目的地までの距離(p=0.07>0.05)と有意差があるとは言えなかった(p>0.05).
考察
本研究では,要支援・要介護高齢者の外出頻度に関わる環境因子について検討を行った.統計結果から外出頻度と道路周辺環境,目的地数,目的地までの距離に有意差があるとは言えなかった.アンケート8の「買い物」を選択した人数が多かったが,外出頻度は少ない傾向が見られた.要因として,買い物に家族と一緒に行く,デイサービス以外に外出する機会が少ないことが考えられる.このことから,趣味,余暇活動,地域の通いの場への参加等を目標とすることで,外出頻度や目的地数の増加に繋がると推測する.今後の課題としてアンケート内容の修正,対象人数の選定について再検討し,本研究で着目した環境因子と外出頻度の関連性について分析を行う必要があると考えられる.
参考文献・引用
- 1)藤堂恵美子ら:地域在住男性高齢者の外出頻度と環境要因 . 理学療法科学 , 30(2); 285-289,2015.
- 2)加藤剛平ら:地域在住要介護者等の外出頻度 に関連する環境因子−通所リハビリテーション 利用者に着目して . 理学療法学 , 38(1); 17-26, 2011.