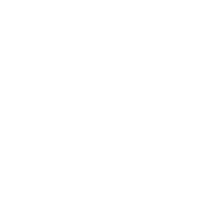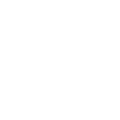高齢者におけるオプティカルフロー刺激を用いた歩行速度上昇の試み
はじめに
要介護状態となる高齢者の主な原因の一つに転倒があり,その要因として歩行速度の低下が挙げられる.高齢者の歩行速度上昇を目的としたアプローチには関節可動域訓練や筋力トレーニングなどがあるが,これらは歩行速度を上昇させるのに数週間を要することが多い.Ludwig ら1)は,周辺視野へのオプティカルフロー(OF)が自己運動感覚に大きな影響を及ぼし,OF を増強した環境での歩行が歩行速度の上昇に寄与することを示している.そこで本研究では,OF を用いることで高齢者の歩行速度を一時的に上昇させることが可能かを検証することを目的とした.
対象と方法
本研究は,65歳以上の自力歩行が可能な男女27名を対象とした.加速距離(3m),減速距離(3m)を含めた16m を最大努力歩行し,中央10mの速度を測定した.課題は,無地シート上での歩行(non-intervention;n),横縞模様シート上での歩行(intervention;i)とした.Ⅰ群(n1→ i → n2),Ⅱ群(n1→ n2→ i),Ⅲ群(i → i → i)にランダムに分類し,10m 歩行を実施した.視覚下方および,上方へのOF を追加するために, 鏡を固定したヘルメットを用いた.各課題の歩行速度はストップウォッチを用いて計測し,Ⅰ群,Ⅱ群,Ⅲ群ともに各3回測定を行った.データ解析は,分割プロット分散分析にて行なった.
結果
分散分析の結果,群間および反復測定の両方で統計的に有意な差が認められた( 群間:p=0.0302, G.eta^2=0.1175, 反復測定:p=0.0270,G.eta^2=0.0897).3回の測定に基づき,各群における測定間の差を以下のように示す.Ⅰ群では,n1とi の測定間で有意な差がみられ(p=0.0046,調整後p=0.0139), 効果量は中程度であったが(G.eta^2=0.2981),i とn2の間では有意差はなかった(p=0.0876). Ⅱ 群でも,n1とn2の間で有意な差が認められ(p=0.0031,調整後p=0.0092),効果量も中程度であり(G.eta^2=0.3274),n2とi の間にも有意差が確認された(p=0.0366,G.eta^2=0.3364).一方,対照群(C 群)では,n1とn2,n2とn3の間ともに有意な差はみられなかった(それぞれp=0.6519,p=0.8694).
考察
本研究では,OF 刺激の増強によって高齢者の歩行速度が上昇することが示唆された.Ⅰ群とⅡ群では,無地シートから横縞模様シート(n からi)への変化に伴い,歩行速度が有意に増加した(Ⅰ群:p=0.0046,Ⅱ群:p=0.0031).この結果は,OF を増強した視覚刺激が自己運動感覚を促進し,歩行速度の向上に寄与している可能性を示している.特に,視野周辺領域へのOF 刺激が視覚誘導自己運動感覚を強化し,歩行速度に影響を与えた可能性が考えられる.視野周辺領域がOF 刺激に伴い,視覚誘導自己運動感覚により身体の移動感覚に大きな影響を及ぼしている.Durgin ら2)は,歩行中にOF が視覚と運動感覚の統合により強化され,自己運動感覚が鋭敏になる.これにより,脳が歩行速度を効率的に認識できるようになり,運動制御が活性化されることで歩行速度が向上する.視覚的なスピード感が適応的に調整され,歩行のリズムやテンポが安定することで,無意識に速いペースを維持できるようになると示唆される.
参考文献・引用
- Casimir J.H.Ludwig et al : The influence of visual flow andperceptual load on locomotion speed. Atten percept psychophys, 80 ; 69-81, 2018.
- Frank H Durgin et al : Enhanced optic flow speed discrimination while walking : contextual tuning of visual coding.Perception, 36(10) ; 1465-1475, 2007.