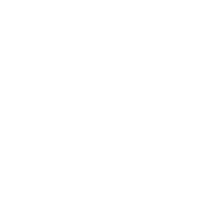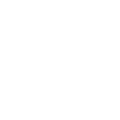小学生サッカー競技における傷害と下肢柔軟性の関連性について −メディカルチェックを用いて−
はじめに
サッカー競技における傷害は下肢において多く,成長期である小学生において,オーバーユースや過負荷などが影響していると考えられている.また, 先輩方の研究においても成長期サッカー小学生78名を対象とした調査にて,約半数近くの選手が下肢に何らかの傷害を多く発生しており,傷害ケアの視点において重要な問題であることが窺えたと同時に,傷害因子に繋がる追及は重要な側面であることが示唆された.
成長期は骨の長径発育に対し筋の発育の遅延が生じるため,筋柔軟性が低下しやすいと考えられている1).そこで成長期のサッカー競技で発生する傷害と下肢周辺筋の柔軟性との関連性について検証した.
対象および方法
<方法>対象者に基本情報(学年,利き足,過去1年間の下肢傷害の有無,傷害内容,受傷時の状況,傷害期間)の収集を実施.また,柔軟性テストとしてしゃがみ込み動作,指床間距離(以下:FFD),臀部踵距離(以下:HBD),股関節外旋・内旋可動域測定を実施した.結果に対し,傷害の有無を目的変数に,各項目の柔軟性テストを説明変数にしたロジスティック回帰分析を行なった.更に,傷害の種類(オーバーユース,非接触型外傷,接触型外傷)を目的変数に,各柔軟性テストを説明変数にした多項ロジスティック回帰分析を行なった.いずれの統計処理においても有意水準5%未満とした.
結果
単純集計の結果,傷害なしが39名,傷害ありが13名だった.(オーバーユース:9名,非接触型外傷:3名,接触型外傷:1名)また,13名のうち8名が6年生だった.利き足は52名中49名が右利きであった.
傷害の有無を目的変数としてロジスティック回帰分析を行なった結果,右股関節内旋可動域に有意差を認めた(p <0.01 オッズ比:1.18).また,傷害の種類を目的変数として多項ロジスティック回帰分析を行なった結果,右股関節外旋・内旋可動域に有意差を認めた(p <0.001).オッズ比:右股関節外旋(オーバーユース:1.65,非接触型外傷:1.24,接触型外傷:1.57),右股関節内旋(オーバーユース:2.40,非接型外傷:2.18,接触型外傷:1.11).
考察
今回,右股関節回旋の柔軟性低下が下肢傷害に関連していることが示唆された.股関節回旋動作はサッカー特有のキック・トラップ・ドリブルなどの基本動作で強調されるため,主として股関節回旋筋群が過活動となり,このような活動の繰り返しが蹴り足側の柔軟性低下に関連している可能性があると考えた.また,傷害が6年生に多い理由として筋力が発達する前段階であり運動強度が高くなるにつれ,骨と筋の成長にアンバランスが生じるためだと考えた.今回の研究を通し,柔軟性が低下した状態で過度な運動を行うと傷害発生やそれらのリスクが増加すると考え,中学生・高校生に向け小学生の時期から利き足を始め,股関節回旋を中心とした柔軟性を高めていく必要があることが示唆された.本研究の結果をもとに柔軟性向上が傷害予防に繋がっていることを把握していくためにも長期的な介入が必要ではないかと考えた.
参考文献・引用
- 倉坪亮太ら:成長期男子サッカー選手における軸足ハムストリングスの筋柔軟性とキック動作時身体重心の後方化との関係.理学療法学Supplement (0);0940,2012.